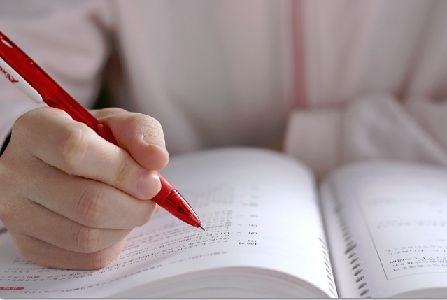税理士になるためには、税理士試験に合格しないといけません。
しかし誰でもが受けれる試験ではありません。
税理士試験には、受験資格が設けられている
税理士試験を受験するには、以下の学識(学歴)が必要です。
国税庁のホームページから受験資格の学識を引用してみます。
【受験資格の学識】
(1)大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者
(2)大学3年次以上の学生で法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
(3)専修学校の専門課程(①修業年限が2年以上かつ②課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者
(4)司法試験に合格した者
(5)旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者
(6)公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る。)
(7)公認会計士試験短答式試験全科目免除者
となります。
噛み砕いて説明すると
◎大学・短大・高等専門学校の経済学部や法学部や商学部の卒業生であること。
◎現役の大学生でも3年生以上(62単位以上取得)の経済学部や法学部や商学部大学生なら受験ができる。
◎専門学校で法律学や経済学の科目を履修した2年以上(1700時間以上)の経験のある卒業生。
(4)から下の司法試験合格者、旧司法試験の第二次試験合格者、公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る。)は資格を取得後、税理士会に申請すると試験を受けることなく税理士の資格も取得できます。
中卒や高卒でも受験はできる!!
学識による受験資格を見ると中卒や高卒だと税理士試験が受けれないことがわかります。※公認会計士を除く
しかし「資格による受験資格」や「職歴による受験資格」も設けられているので、それらの資格や職歴があると受験することができます。
【資格による受験資格】
(1)日商簿記検定1級合格者
(2)全経簿記検定上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る。)
(3)会計士補 ※会計士補は現在なくなった資格です。
(4)会計士補となる資格を有する者
【職歴による受験資格】※通算2年以上従事した者
(1)弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務
(2)法人又は事業を営む個人の会計に関する事務
(3)税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務
(4)税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務
(5)行政機関における会計検査等に関する事務
(6)銀行等における貸付け等に関する事務
【資格による受験資格】【職歴による受験資格】以外にも公認会計士を目指すという選択肢もあります。
公認会計士は、中卒や高卒の方でも受験できます。
公認会計士は、難易度が高いですが、合格すると税理士の試験を受けずに税理士の資格も同時に取得できるので、公認会計士の資格を取得するというのも一つの手かもしれません。
他にも税理士の試験を受けずに取得する方法として、税務署をはじめとした国税官公署で23年以上働いたうえで指定の研修を受けた人は、税理士の資格が取得できます。
まとめ税理士の受験資格
以下の方に受験資格があります。
◎大学・短大・高等専門学校の経済学部や法学部や商学部の卒業生
◎現役の大学生なら3年生以上(62単位以上取得)の経済学部や法学部や商学部大学生
◎専門学校で法律学や経済学の科目を履修した2年以上(1700時間以上)の経験のある卒業生
◎日商簿記検定1級合格者または、全経簿記検定上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る。)
◎弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務に2年以上従事した者
◎法人又は事業行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
◎税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務に2年以上従事した者
◎税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務に2年以上従事した者
◎行政機関における会計検査等に関する事務に2年以上従事した者
◎銀行等における貸付け等に関する事務に2年以上従事した者
税理士試験を受験しなくても、税理士の資格が同時に取得できる資格や経験
◎弁護士(司法試験合格者)
◎公認会計士
◎税務署・国税官公署で23年以上勤務し指定の研修を受けた者